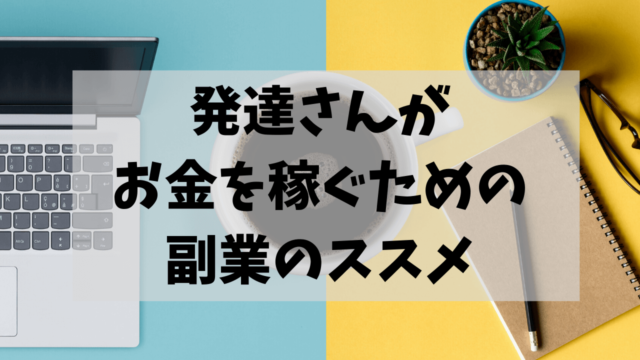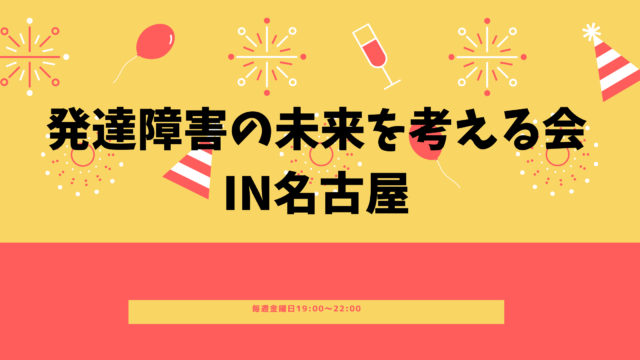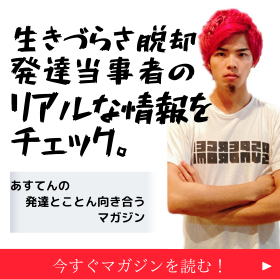どうも!あすてんです。
発達障害の方がよく悩んでいる問題として、聴覚の過敏が挙げられると思います。
聴覚過敏とは、発達障害を持っている方によく見られる”感覚過敏”という特性の一種です。
ある特定の感覚が人よりも過敏なことで、ちょっと疲れてしまう。
光や触覚など、色々ありますが、そのなかで「音」に関する感覚が鋭いのが聴覚過敏です。
この聴覚過敏の特性を持っている人は、アスペルガーの人に多い印象です。
具体的には「都会を歩くときにストレスが半端ないって!」とか「こどもの甲高い声が耐えられない」といった悩みが多い。
ぼくも昔からずっとこの問題には悩んでいて「どうしたものか」と毎日頭を抱えていたものです。
今だと、カフェで働いていることが多く、様々な音と戦ってきました。
そんな状況のなかで、試行錯誤をした結果、昔と比べてかなりストレスが減ったんですね。
てなわけで、今回は「聴覚過敏の対策法を3つ」考えてみたので順番に解説していきます。
実体験を盛り込んで書いていくので、ぜひぜひ「聴覚過敏をどうにかしたい!」という方はご覧ください。
目次
そもそも聴覚過敏とは一体なんぞや?
読んで字のごとく、聴覚にかなり過敏性がある人のことを言います。
はじめにも書いたとおり、発達障害のひとの特性の感覚過敏の一種でもありますね。
発達障害でも感覚過敏でも、少数派の人あるあるですが、多くの人に相談するときの「私もそれあるある!」とはちょっと違くて。
些細な音もすごく気になってしまうパターンが多めです。
たとえば、以下の通り。
- 時計の秒針がすごく気になる
- 突発的な音(お皿が割れてしまったり)に弱い
- 子どもの甲高い声が耐えられない
どの音にダメージを受けるかは人それぞれです。ただ、総合的に音に対して弱いですね。
また、同時に音を拾ってしまうことも多い。
仕事中に、目の前で上司が話してくれているのに、電話対応の声やほかの人の声が入ったりと、雑音が混じりやすい。
そういった特徴もあります。
聴覚過敏のイライラはウォークマンで例えると分かりやすい?

そんな、聴覚過敏の人が感じる、イライラやストレスは、はなかなか人には伝わりません。
細かく伝えようとしても「細かいやつだな」と思われてしまうのが関の山。
というのも、感じている世界が違うので、なかなか理解してもらうことは難しいんですね。
そんな聴覚過敏のイライラは、例えるとするとすべての音量がマックスのウォークマン。
高い音を強くする。低い音を弱くする。
そういった機能がウォークマンのイコライザ機能にはあります。
比べて、聴覚過敏の人の多くのタイプは、音の聞き分けが難しい。
居酒屋でいうと、全ての音を均等に拾ってしまうのと一緒です。
店員さんの掛け声も、周りで盛り上がっている人たちも、一緒に飲んでいる仲間の声も同じボリュームなので、聞き分けが難しい。
多くの人は、状況によってどこが大切な音なのかを汲み取り、自動的にボリュームの調整してくれる機能があります。
ただ、聴覚過敏の人はボリュームが全て100%になっているから、疲れる。
と考えるとイメージが掴みやすいかもです。
聴覚過敏のイライラを防ぐための対策
聴覚過敏の対策は、人それぞれ違うので、むずかしいとは思います。
音を避けて生きていくことは難しいし、生きていくうえで、絶対に音と関わっていかんといけないのは確実です。
完全に閉め切って1人の空間で生きていくならいいのですが、、
「ただそんなこと言っても向き合わないといけない…。」っていうのが辛いところ。
自分なりに考えてみて、手段としては以下の3つ。
- 環境をガラッと変える
- 理解されやすい状況を作る
- 自己防衛を徹底する
順に解説します。
①環境をガラッと変える
日常生活の大半で音にストレスを感じるなら、環境を思いっきり変えてしまうのもアリです。
その前には、どの環境下で自分が一番ストレスを感じるのかを考えるとOK。
ここだけの話、ぼくは実家での音のストレスをかなり抱えていました。
本当に些細なことが気になるので「吸引力の変わらないダイソンの吸引音」「オカンが朝一で思いっきりカーテンを開けるルーティン」「風通しのよさから勢い良く閉まるドア」など、、
聴覚過敏のぼくからすると、なかなかの強敵ぞろいだったんです。
実際、このどれかに当てはまる瞬間に、駆け込んで文句を言っていた時期もあったくらい。ただ、根本的な解決にはならないんですよね。
お互い我慢しないといけないのは損しかしないので。
ってことで、静か目なシェアハウスに引っ越したりしました。
「アスペだからシェアハウスのほうが色々ときついんじゃ?」と思いがちですが、そんなこともなかったです。
オーナーの方がおとなしい性格だったり、頻繁にコミュニケーションをとるより個人を大切に!という方向性だったので、一人暮らしみたいでストレスフリーでした。
この例だと少し特殊ですが、、
思い切って環境を変えることで改善されることもあります。
②理解されやすい状況を作る
環境をガラッと帰ることができたら手っ取り早いものの、仕事となると話は別。
「仕事の環境を変えるためにとりあえず転職するぜ」なんてフットワークの軽い方はなかなかいません。
そんな人にオススメなのが、理解されやすい状況を作ることです。
ある程度自由が利かないときは、限られた状況のなかでできることをやる。
0には抑えられないけど、少しでも軽減する方向に寄せていくのが賢明かと思っています。
たとえば、職場の音にストレスが強い場合、自分の主張だけで「こう変えてよ!」という意見はどうしても通りにくいです。
なぜなら、職場全体でのルールがあるから。やっぱり、組織はえらい人や多数決で成り立ってしまうのでしょうがないです。
「そんなこといっても辛いもんは辛いんじゃ」ってなるんですが、少しでも軽減できるように説明できると結構変わりますよ。
ぼくはカフェで店長を経験していましたが、聴覚過敏がしんどくなることは確実だったので、事前に伝えておきました。
内容はシンプルに、「あまりにもしんどい時は少しだけ外で休憩するわ!」とか「キツいときはイヤホン装着するね!」とかです。
ただ、職場や労働環境によって大きく変わると思うので、ちょっと難しいかもしれません。
出来るなら伝えてみて様子を見るのは全然アリだと思います。
ここでのポイントは「配慮してほしい」と伝えるのではなく、「状況によってはこうしたい」という折り合いをつけると、平和に問題を解決できると思います。
どうしても社会は多数派なので、うまく立ち回るためにも伝え方っていうのは大事です。
その方法をうまく掴めるようになると、少数派でもかなり生きやすくなると思いますよ!
③自己防衛を徹底する
最後に自己防衛です。シンプルに音を防ぐ手段をとにかく試す。
私生活や通勤途中など、日常の音に対しての対策法ですね。
代表的なもので言うと、
- イヤーマフ
- 耳栓
- デジタル耳栓
- ノイズキャンセリングイヤホン
です。
イヤーマフとかだと、見ての通り防音性の高さがウリっていう感じですね。ただ、場合によって「ヘッドホンで音楽聞いてるじゃん」と言われかねないのが少しネック。
その点、アマゾンで評価の高いキングジムのデジタル耳栓とかは、発達障害を持っている方と話している時に話題に出てきますね。
そして個人的にオススメなのは、AppleのAirPods proです。ちょっと値段が張りますが…。
まずおしゃれだし、外の音と周波数で打ち消してくれます。さらには、髪の毛に隠れやすいし持ち運びもしやすい。
ワンタッチでのノイズキャンセリング操作も簡単で音楽も聴ける優れものです。
頻繁なコミュニケーションを必要としない仕事(事務とか)であれば、このようなアイテムを使って、大幅にストレスを軽減できる可能性もあると思います。
状況によって使い分けてみてください。
聴覚過敏でいいと思うこと
昔は聴覚過敏である自分は、かなり周りに対してもイライラしていました。
ただ、色々と試行錯誤を通して、最近わかったことが1つあります。
それは、聴覚過敏は体調管理に役立つのでは?という仮説です。
聴覚過敏持ちだけど、おれは体調管理に役立っている。
いつも以上に音が大きく、鼓膜に響くような感覚が強いときは「疲れているな」と把握できる。
特性や弱さも、悪化したときに自分のストレス管理の指標にするといいよね。
— あすてん(アスペルガー店長🔥) (@Kojirase_tencho) February 27, 2020
どういうことかというと、上のツイートの通り。
聴覚過敏がひどいときは寝不足だったり、体調が明らかにわるかったりと、健康状態が密接にかかわっていたことが多かったんです。
反対に、ものすごく元気なときは、いつもよりも音に対しての耐性が強かったり。
これって逆に、過敏の度合いによって「自分の体調を把握できるんじゃないか」ってことに気づけました。
もしかしたら、聴覚過敏が強いとき・弱いときを分析してみると、自分を知るきっかけに繋がるかもしれません。
過敏である特性と向き合うのは大変ですが、その過敏性を逆手にとって、活かすこともできるのではないでしょうか。
できることから対策していこう
今回は、つい音に過敏になってしまいイライラする、聴覚過敏の対策について、書いてみました。
人それぞれ、状況は違うかもしれません。
ただ、自分に出来る対策を打ちつつ、ストレスを軽減したり、うまく向き合っていくことで状況は少しずつ改善されると思います。
とくに、防音対策グッズなどは、私生活や休みの日など、日常生活の中で大きな効果を発揮するので、ぜひ試してみてください。