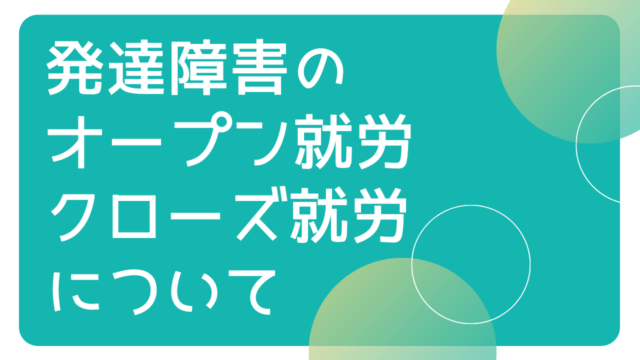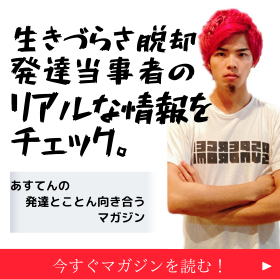ども、あすてんです。
アスペルガー症候群という先天性の発達障害を持っていながらも、名古屋市のカフェで店長をしています。数ヶ月前にこのようなツイートをしました。
うつでも精神障害でも何かを乗り越えてきた人は、一当事者として、ブログでもツイッターでも情報発信するのをオススメしたい😌単純にストレス発散になるし、頭の中の整理も繋がる。何よりも自分の体験談によって日本中の誰かが変わるきっかけを持てたら素晴らしいことだしね🌸辛い経験は活かすべき。
— アスペルガー店長🔥あすてん (@Kojirase_tencho) June 20, 2019
うつでも精神障害でも何かを乗り越えてきた人は、一当事者として、ブログでもツイッターでも情報発信するのをオススメしたい😌単純にストレス発散になるし、頭の中の整理も繋がる。何よりも自分の体験談によって日本中の誰かが変わるきっかけを持てたら素晴らしいことだしね🌸辛い経験は活かすべき。
学生時代までは精神的に不安定な部分が多く、色々なことに悩んだり苦しんだりしましたが、今ではかなり落ち着くように。
その経験を生かして、昔の出来事や自分が乗り越えてきたことをつらつらとTwitterやブログなどで発信しています。
そんな中で、情報発信を毎日することで様々なメリットを感じました。
僕の場合だと、情報発信経由でお店に30人以上の当事者の方が県外・県内問わずに遊びに来てくれたりですね。
ただ、そのほかにも多くのメリットがあるので、ぜひ当事者の方に伝えたいなという思い出ブログを書いています。
ということで今回は、うつや精神障害で悩む当事者こそ情報発信するべきという理由について解説していきます。
後半では情報発信の仕方についても簡単に解説するので、ぜひぜひ読んでみてください。
目次
うつや精神障害で悩む当事者こそ情報発信をしよう

うつや精神障害、発達障害などマイノリティな立場の人が情報発信をするべき理由は、自分の体験談によって誰かに影響を与えられるという点です。
上記ツイートだと最後の文章のところですね。
もちろん頭の中の整理ができたり、ストレス発散にもなるのですが、当事者目線の発信をすることで、多くのメリットがあるんですよね。
なので、具体的に当事者目線で発信をするべき理由とそのメリットについて解説していきます。
ざっくりまとめると
・発信することにめちゃくちゃ価値がある
・価値提供によって社会的意義を感じられる
・仲間が増える
解説していきます。
発信することにめちゃくちゃ価値がある
そもそも論として、なぜ当事者が情報発信をするべきなのか。
その理由は、発信者が少なく情報の価値がかなり高いからです。
普通の人が今まで体験してきたこと
当事者が今まで体験していること
と情報をざっくり分けても、後者の方が圧倒的少数なので、そういった情報は、かなり希少価値が高いということになりますよね。
発達障害やうつなどの精神障害を経験している人は多いかもしれませんが、発信している人の数はかなり少ないんですよね。
そんな中、いち当事者の意見として、経験してきたこと・工夫してきたことを発信することはすごく価値のある行動なんです。
だって、リアルな悩みを抱えるそれぞれの当事者が試行錯誤して乗り越えてきた生の情報や経験ってかけがえのないものですよ。簡単に手に入るものじゃない。
人それぞれ悩みの解決方法は違うかもしれませんが、等身大でぼくたちが悩み、向き合ったことは、今悩んでいる多くの人を救えるかもしれないのです。
価値提供によって社会的意義を感じられる
情報発信をすることで社会的な意義を感じやすくなります。
社会的意義とは簡単にいうと「社会の役に立っているぜ」と実感できること。
いろいろな発達当事者の方にあってきた統計なんですけど、多くの方が接客や介護など人と関わる仕事をしている人が多かったんですよね。
一般的には発達特性で苦手分野だったり、うまくいかない傾向が強いのに、そういう仕事を選んでしまう背景には「自分が社会に存在している意味」を見出したいのかもしれません。
そんな人にとって、情報発信はまさにうってつけ。
自分が今までに経験してきたことをシェアすることで、他の方に生きるための希望を与えることができる可能性は高いですし、自分自身も社会にの役に立っていることを実感できます
仲間も増えます
情報発信を続けると仲間がどんどん増えます。
具体的には
ツイッターでいいね!やコメントをしてくれる人
情報発信をしている姿をみて協力してくれる人
リアルで応援してくれる人
ですね。
理由としては情報発信者が少ないという点に加えて、マイノリティの立場から発信している人はさらに少ないです。なので、フォロワーさんからしたら「この人と繋がっておきたい」と思ってもらえるんですよね。
そして、仲間が増えることによって何が良くなるのかというと、同じ価値観を持った人と繋がりやすくなるんですよ。
簡単にいうと気の会う人に自動的にマッチングするという感じですね。
発信をしていく中で、だいたい見ている側の人は、自分にあっているかあってないかを文章で察知します。
そのときに、自分と似ているなと感じる人はより自分に共感してくれたり、協力してくれたりと、心強い味方になってくれます。
特に発達障害当事者だと、芯では強いものを持っていたり、個性豊かで面白くても、表面的なコミュニケーションや人と違うクセなどで、一番最初の人間関係でつまずく人も少なくないはず。
ただ、先に情報を発信して自分を知ってもらうことで、そのような会った時のギャップや駆け引きがなくなるので、人間関係の構築でもストレスフリーになりやすいというメリットがあるんですよね。
今後自分を伝える個の時代の中で、情報発信に力を入れるということは副次的にも大きなメリットがあります。
よくある質問について答えます

情報発信をする意味や価値はお伝えしましたが、大半の方はこのようなことを思うのではないでしょうか。
そんなに障害に対して乗り越えてきた体験がないから、何を発信していいかわからないし、発信することって結構怖いなぁ…
そんな人のために事前に質問に答えていきたいと思います。
✅乗り越えてきたというハードルは低くても大丈夫です
発信をするときに「乗り越えた経験がないから発信できない」という方がいますが大丈夫。
どれだけ小さな工夫や改善でも、小さな壁を乗り越えた経験は、いま誰かが悩んでいる問題でもあります。
悩みの大きさも人それぞれ。自分が軽く乗り越えたことが相手にとっては難しく、体験談が欲しい人もたくさんいると思うんですよね。
また、発信できる経験がないとしても、これからどうやって乗り越えていくかっていう目標を立てて発信するのもいいかと思います。
その過程で共感し合えたり、問題解決の糸口を一緒に探っていくのも大きな価値になりますからね。
大事なのは当事者の目線でどう考えているかを等身大で伝えることでして、悩みの大きさなどは気にしなくていいです。
✅発信するのが怖いです
これもよくある質問だと思っていて、アンチに絡まれるのが怖いと思う方もいるのではないでしょうか。
たしかに、自分が経験した発信内容について非難されたり、心無いリプライが飛んでくるかもしれません。ただ、それは発信をしていく上で避けられないことかもしれません。
全世界の人が情報を見るわけなので、ごく少数の人はあなたに対して攻撃的な発言をしてくるかもしれません。
ただ、同時に多くの当事者と繋がれたり、感謝される割合ことも増えていきます。どっちかというとその割合の方が圧倒的に多いです。
ぼく自身4ヶ月以上SNSで発信をしていますが、アンチに絡まれたことって本当に少ないです。
ごく少数なアンチに対して気を使うより、自分を応援してくれる多くの仲間に対して「どうやったらさらに貢献できるか」を考えたほうが効率がいいですし有意義。
いまアンチの人も悩みのレベルやタイミングが違うだけなんだと割り切り、いつか理解してくれて仲間になってくれたらいいなくらいの気持ちが一番安定します。
うつ・精神障害当事者の情報発信の仕方とは?

初めて情報発信する人は何をすればいいかわからないと思いますが、意識するべきことは「相手がその情報を見てためになること」をつぶやきましょう。
相手がその情報を見て「ためになること」を呟こう
大前提として、相手のためになる情報を発信しないと意味がありません。ためになる情報かどうかの違いは以下の通り。
ためにならない:ランチ食べたおいしい。友達と遊園地行った楽しい。同僚がうざい。
ためになる:〜〜の経験でこれが克服できました。この対策をすると楽になります。
ぶっちゃけランチ行ったとかはどうでもよくて、あなたが過去に色々な思いで経験してきたこと、考えてきたことについてフォロワーさんは知りたいと思っています。
なので、発信するときに「読んだ相手がうんうんとうなづける」内容かどうか考えるとわかりやすいです。
ほかにも、発信内容としては
- いきづらさが解消される考え方
- 福祉の制度/おすすめの心療内科
- 辛かったときに役立った情報
- 勇気が出るような言葉
- 日頃の経験やそこから得た気づき
- 過去の自分の経験談
などなど。
ほんの些細なことでも、相手からしたら目から鱗なん情報ということもよくあるので、まずは上の基準を満たしていることを発信してみましょう。
自分の中では普通だと思って発信したことが大きな反応をもらえることもあるかもしれません。
そのためには自分の棚卸しが必要
そして上記のような内容の情報を発信するには、過去の自分が経験してきたことを思い出す棚卸し作業が必要です。
具体的には3年前の自分を想像して、過去の自分がどう言うことに悩み、どんな出会いやきっかけで改善することができたのかを紙に書くなど。
ちなみに僕の場合だとこんな感じ。
ここで思ったことは
現状の自分がうまくいくためには、自分の力でどうにかするのではなく、周りの人が向き合ってくれる環境や配慮が必要だ
ということです。
そこでぼくは、まずは現状を改善する前に、いまある環境の整理をするべきだと感じました。そこで発信した内容がこちら。
発達障害で悩んでいる人って、現状の克服をするよりも、まずは「自分の居場所を見つけるべき」だと思う。というのも、認めてくれる人間がいる場所でないと、現状を打破する力が湧き出てこないと思うからです。改善点と向き合う前に、今いるコミュニティーや人間関係の重荷を切り捨てよう。
— アスペルガー店長🔥あすてん (@Kojirase_tencho) May 27, 2019
こんな感じで、昔悩んでいた自分の状況を整理してみて、そこからどういう感がに至ったか。何をしたかを発信するといいです。
思い出すのが難しい方だったら、過去の友達と話してみてもいいですし、学生時代のSNSアカウントや親に聞いてみてもいいですね。
相手のことを想像するのが苦手でも、過去の自分を元に考えることはわりかし簡単なので、ぜひやってみてください。
さあ、情報発信を始めよう
ということで今回の記事は終わりです。
発信媒体はなんでもよくて、伝える練習をすればするほどリアルでもいかせられるスキルが身につきます。
YouTubeを頑張る:リアルの会話能力が向上
ブログ・ツイッターを頑張る:文章力が向上
得意な方法を選べばいいと思いますが、どちらにしてもコミュニケーション面の大きな支えになってくれるのも情報発信のいいところですね。
最初は慣れないかもしれませんが、ゆるくでも続けていけば伝える能力も向上していくと思うので、ぜひ今からでも発信してみてください。